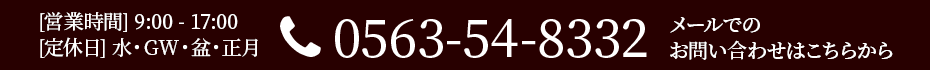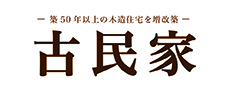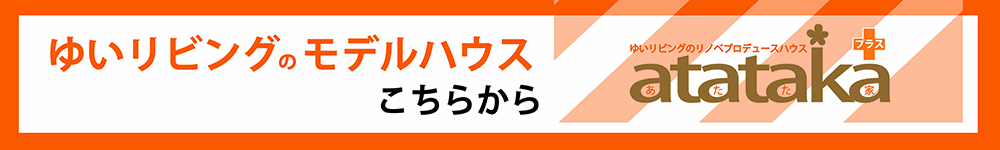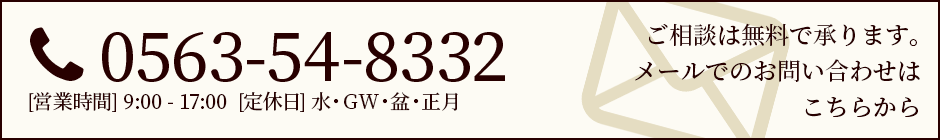物事の本質は、事実を逆算
研修
先日、6か月間の研修を終えた藤井君は、
学んだことを最後のアンケートでこう書いていました。
「全員がお客様に向くことが必要」
「苦言をくださるお客様は、改善すべきところを無料で教えてくれるコンサルタント」
「商品は、売るのではなく『買う』もの」
この三つの報告を見た時、研修に参加してもらって本当に良かったと思いました。
良かったと思った理由は一言でいうと
【物事を見る目線が自分ではなく、自分以外になっている】
もっと簡単に書くなら
【主語が自分から「自分以外」になっている】
ということでした。
この仕事はそもそも誰のためのものなのか
「仕事をする」とよく言います。
正確には「仕事をさせていただいている」です。
なぜなら、その仕事は発注者なしに成立しないからです。
主語は自分ではないのです。
主語が自分になる時は、発注者となる時のみと言えます。
社会人になるまでに、なぜこの仕組みを強く勉強する機会が無いのかが疑問です。
最近は「個を重んじる」がスタンダードな考え方です。
戦後も昭和を終えるまでは上下関係は非常に厳しい時代でした。
上下関係とは、単なる上司部下ということではないです。
自然と「頂いている」という態度にさせられるため、
上司は勘違いでも「有難いと感じているな」と思えたのでは
無いかと思うのです。
ですから、良くも悪くも自然に個人より組織を重んじる風潮がありました。
しかし現代は少子化のあおりも受けているのだろうとは思いますが、
上司が部下に必要以上に気を遣う時代となっているようにも思います。
個を重んじる=我がままにふるまってよい、ではないのですから。
当然発注者があってこそのお仕事であり、その依頼に対して結果をつくる事で対価を頂ける。
その対価を頂けることによって、自分の生活を維持向上できるのです。
対価を頂くことができる仕事ができて、初めて胸を張って「仕事をした」と言えるのですから、本来仕事ができる自分になるまでは個を重んじる必要性は薄いと思うのです。
「時給●●●円」などと、拘束する時間への対価としてしか表現できない社会の仕組みにも問題はなるのだと思いますが、本来は「依頼に対しての結果=対価」という考え方が基本にあり、しかしそれでは不安定なため、安定した生活環境をつくらなければ安心して雇用され続けられないので、「月給●●円」にしましょう、という共通の認識がもっともっと必要なのではないかと思うのです。
依頼者が神様と言っているわけでないです。
依頼者は自分のできない事を対価を支払い、結果をつくってもらうのです。
そこに「当たり前」ではなく「有難う」という気持ちをもち伝えることで、ここで初めて「お互い様」というあるべき姿ができるのです。
分かっている人は、いばりません。
分かっている人は、謙虚です。
分かっている人は、素敵な仕事をしたり、結果を得ています。
どんなことも、気付きがあって始めて行動へと移れるのですから、今回藤井君が得た気付きは、藤井君にとっても宝物ですし、その藤井君の行動に影響される私達社員や協力業者さん、お客様にとっても宝物と言えますね。
こう偉そうなことを書いている私は、全て出来ていることではないからこそ、弱い自分の退路を無くすために書いている面もあります。
物事の順序を逆算すると、本質が見えてきますよね。

先日、6か月間の研修を終えた藤井君は、
学んだことを最後のアンケートでこう書いていました。
「全員がお客様に向くことが必要」
「苦言をくださるお客様は、改善すべきところを無料で教えてくれるコンサルタント」
「商品は、売るのではなく『買う』もの」
この三つの報告を見た時、研修に参加してもらって本当に良かったと思いました。
良かったと思った理由は一言でいうと
【物事を見る目線が自分ではなく、自分以外になっている】
もっと簡単に書くなら
【主語が自分から「自分以外」になっている】
ということでした。
この仕事はそもそも誰のためのものなのか
「仕事をする」とよく言います。
正確には「仕事をさせていただいている」です。
なぜなら、その仕事は発注者なしに成立しないからです。
主語は自分ではないのです。
主語が自分になる時は、発注者となる時のみと言えます。
社会人になるまでに、なぜこの仕組みを強く勉強する機会が無いのかが疑問です。
最近は「個を重んじる」がスタンダードな考え方です。
戦後も昭和を終えるまでは上下関係は非常に厳しい時代でした。
上下関係とは、単なる上司部下ということではないです。
自然と「頂いている」という態度にさせられるため、
上司は勘違いでも「有難いと感じているな」と思えたのでは
無いかと思うのです。
ですから、良くも悪くも自然に個人より組織を重んじる風潮がありました。
しかし現代は少子化のあおりも受けているのだろうとは思いますが、
上司が部下に必要以上に気を遣う時代となっているようにも思います。
個を重んじる=我がままにふるまってよい、ではないのですから。
当然発注者があってこそのお仕事であり、その依頼に対して結果をつくる事で対価を頂ける。
その対価を頂けることによって、自分の生活を維持向上できるのです。
対価を頂くことができる仕事ができて、初めて胸を張って「仕事をした」と言えるのですから、本来仕事ができる自分になるまでは個を重んじる必要性は薄いと思うのです。
「時給●●●円」などと、拘束する時間への対価としてしか表現できない社会の仕組みにも問題はなるのだと思いますが、本来は「依頼に対しての結果=対価」という考え方が基本にあり、しかしそれでは不安定なため、安定した生活環境をつくらなければ安心して雇用され続けられないので、「月給●●円」にしましょう、という共通の認識がもっともっと必要なのではないかと思うのです。
依頼者が神様と言っているわけでないです。
依頼者は自分のできない事を対価を支払い、結果をつくってもらうのです。
そこに「当たり前」ではなく「有難う」という気持ちをもち伝えることで、ここで初めて「お互い様」というあるべき姿ができるのです。
分かっている人は、いばりません。
分かっている人は、謙虚です。
分かっている人は、素敵な仕事をしたり、結果を得ています。
どんなことも、気付きがあって始めて行動へと移れるのですから、今回藤井君が得た気付きは、藤井君にとっても宝物ですし、その藤井君の行動に影響される私達社員や協力業者さん、お客様にとっても宝物と言えますね。
こう偉そうなことを書いている私は、全て出来ていることではないからこそ、弱い自分の退路を無くすために書いている面もあります。
物事の順序を逆算すると、本質が見えてきますよね。